日本の農業は、地理的・人口的な制約に適応し、古くからの伝統と先進技術を組み合わせた複雑なモデルを示しています。国内総生産(GDP)の1%のみを占めるものの、この分野は食料安全保障、農村コミュニティの維持、新興農業技術の開発において重要な役割を果たしています。耕作可能地の12%しか持たず、消費食料の60%を輸入に依存する日本は、集約的で知識集約型の農業のモデルです。本稿では、科学的視点から日本農業の主要構造、革新、課題、将来展望を分析します。
1. 歴史的背景と構造的変遷
(1)戦後の農地改革**
- **農地再分配(1946–1950年):** 連合国軍占領下で実施された農地改革により、農地の80%が小作農から自作農へ移管され、家族経営農業の基盤が形成されました。
- **農業基本法(1961年):** 機械化や米などの戦略作物の価格支持を通じた生産性向上を目標としました。
(2)近代農業への移行
- 米の集中生産:** 文化的・政治的作物としての米は、日本の水田の95%を占めます。
- 1990年代の多角化:** 米消費の減少を受け、小麦、施設野菜、高級果物(例:夕張メロン)の生産が拡大しました
2. 現行構造:小規模経営から産業連携まで
(1)主要特徴
- 小規模経営の主流:** 平均農地面積は2.7ヘクタール(米国178ヘクタールと比較)。
- 農業人口の高齢化: 農業従事者の平均年齢は 67 歳で、65% が 65 歳以上です。
- **農業協同組合(JA)の役割:** 980万人の会員を擁するJAネットワークが金融、販売、資材供給を管理。
2)戦略的作物
- 米: コシヒカリなどの高級品種を含む年間750万トンの生産。
- 施設野菜:** 二酸化炭素・湿度制御技術を用いたトマトやキュウリの通年生産。
- 畜産: 北海道の大規模酪農や和牛(2022年の輸出額4億ドル)の生産。
3. 技術革新:ロボット工学から垂直農業まで
(1)機械化とロボット工学
- 自動運転トラクター:** クボタなどが開発したGPS連動のスマート農場管理システム。
- 収穫ロボット:東京大学のプロジェクトでピーマンやイチゴの収穫に機械視覚を応用。
2)都市農業と垂直農業
- 植物工場: LED照明と水耕栽培による葉物野菜の生産(スプレッド社は日産3万株のレタスを生産)。
- 閉鎖環境農業: 水使用量95%削減、農薬不使用を実現。
(3)バイオテクノロジー**
- 耐性品種の開発:** 塩害耐性遺伝子組み換え米(理研と東北大学の共同研究)。
- – **微生物肥料:** 窒素吸収を改善する土着微生物の利用。


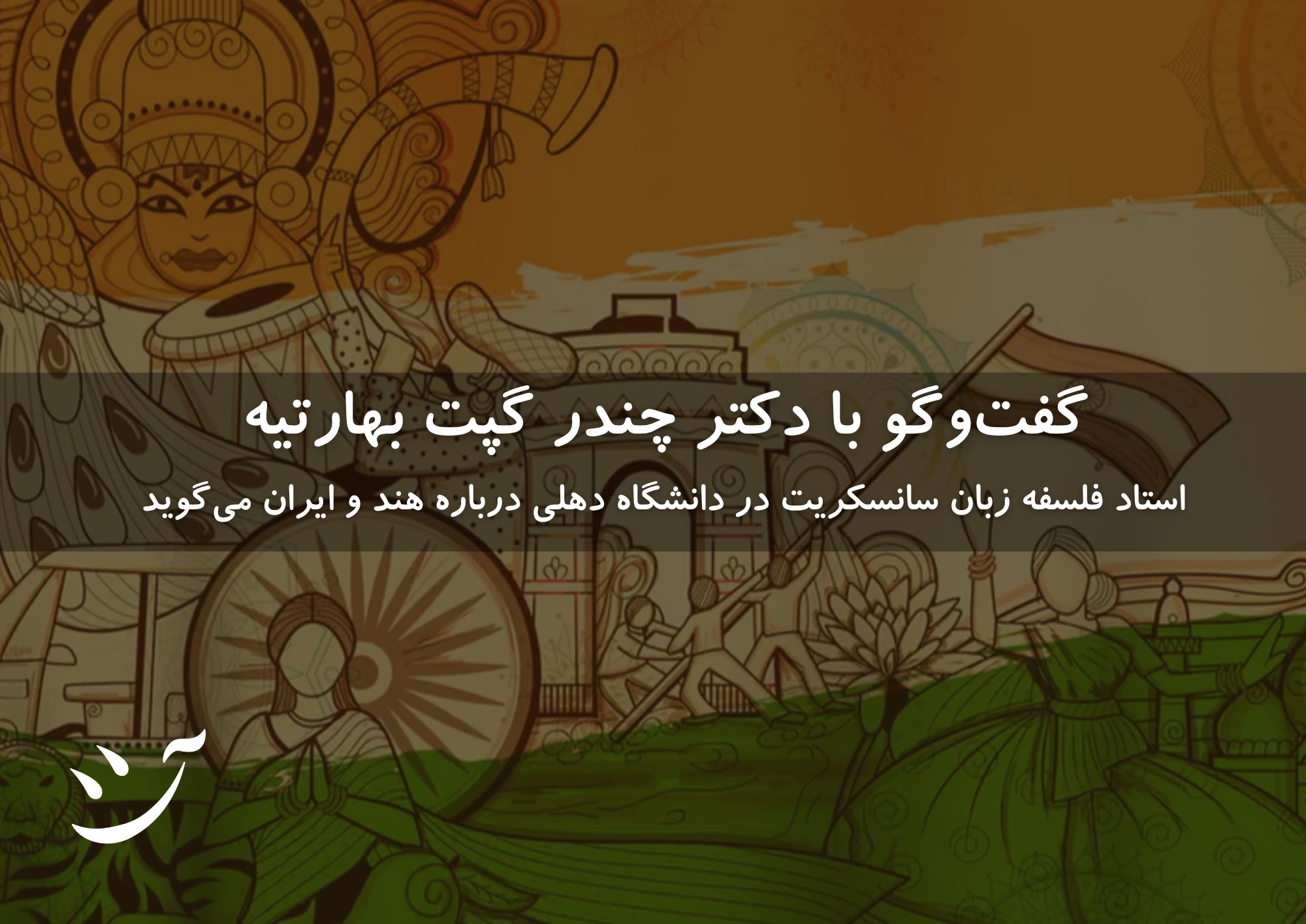

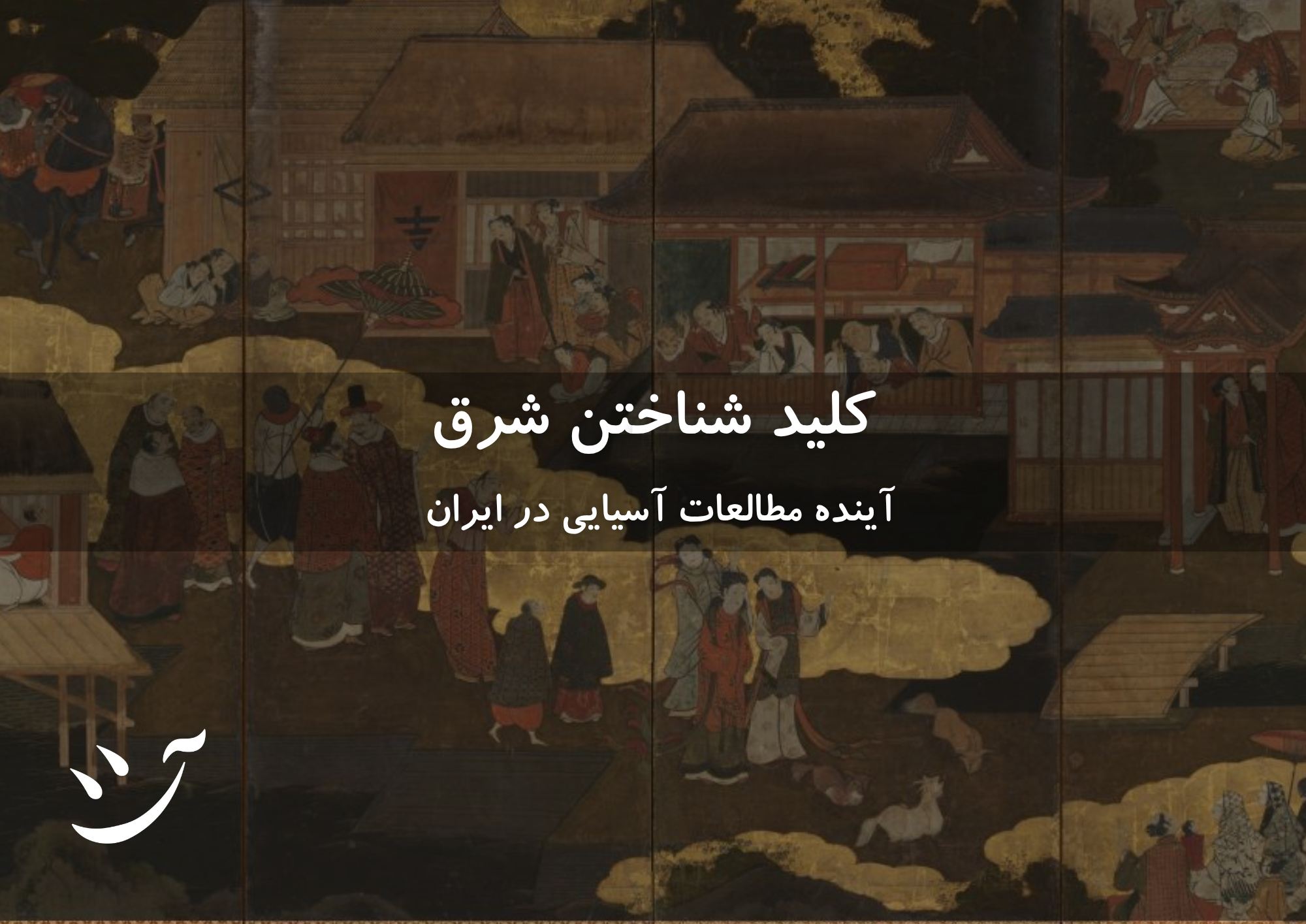

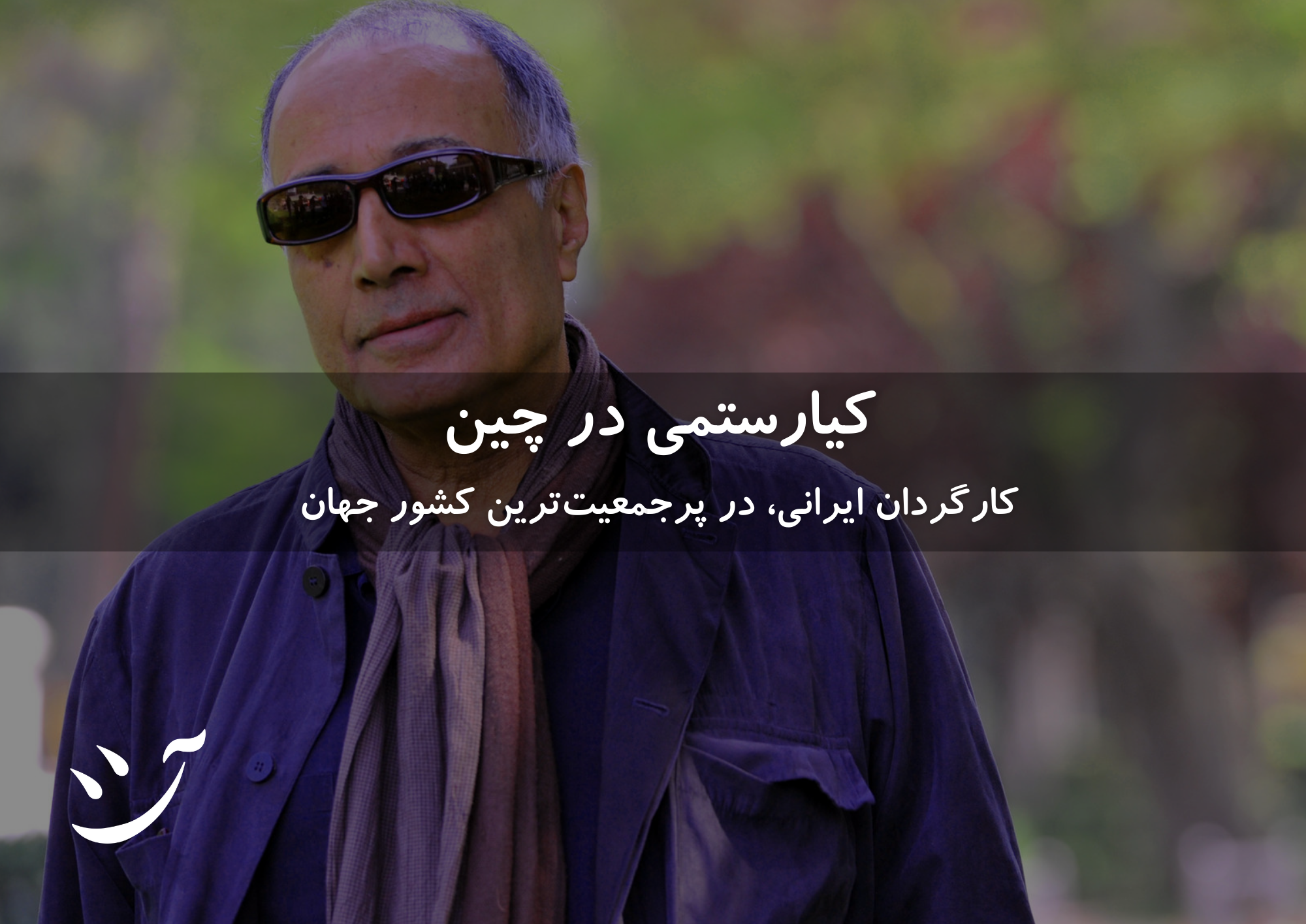
نظرات کاربران